こんにちは、のりせんです。
皆さんの中で、サラリーマンやってる人いますか?
サラリーマンしていると会議によく参加することでしょう。
さらに、議長として、司会をされる人もいるでしょう。
もし、会議で司会をされる人がいましたら、うまく会議を進めようとして、困ったことはないでしょうか?


いつも会議の時間が長くなってしまうんだよね!

議論がまとまらなくて大変だよ!
会議で司会をするとき、いろんな悩みがありました。
① なぜだか、いつも議論がまとまらない。
② 会議が終わりに差し掛かっても、何も決まらない、決められない。
③ 参加者が自分の意見を好き勝手に発言して、収拾がつかない。
④ みんなが会議の時間を気にしないで発言するので、会議の時間がいつも長い。
⑤ よく議論が横道にそれてしまって、会議を開いた目的からずれてしまう。
そんな悩みを持っていたのりせんが、今回紹介する本を実践することで、とてもスムーズに会議を進めることができるようになりました!!
その本は、
田村洋一さんの 「プロファシリテーターのどんな話もまとまる技術」
① 会議の司会者として、うまく話をまとめることができるようになった
② 自分が望んだ方向に話を展開できるようになった
③ 今後につながる結論がだせるようになった
④ 会議時間がとても短くなった
みんなの話をうまくまとめられるようになったら、すごく気持ちいいですよね。
ですので、どのようにすれば悩みが解決するのか、説明していきます。
はじめに
ファシリテーションとは?
みなさんはファシリテーションという言葉を知っていますか?
会議やミーティングを円滑に進める技法のこと
<具体的な行動>
① 参加メンバーの発言を促す
② 多様な意見を瞬時に理解、整理する
③ 重要なポイントを引き出しつつ、議論を広げる
④ 最後には議論を収束させて、合意形成をサポートする
ファシリテーションとは、会議の進行をうまく進めるコツのようなものです。
そして、今回紹介する本の題名にもなっている「ファシリテーター」というのは、ファシリテーションの技術を使って会議を円滑に進める役割を担う人のことをいいます。
ファシリテーションの技術を使って、会議を円滑に進めるう役割の人
つまり、会議でうまく立ち回れる司会者のことです!
優秀なファシリテーターは、このファシリテーションの技術を使って議論を進め、会議の最後には、参加者みんなが腹落ちする納得感を持てるような結論を生み出すことができるのです。
話がまとまるとはどういうことか?
話をまとめるために、してはいけないこと
そもそも「話がまとまる」って、どういうことなのでしょう?
「話がまとまる」というのは「問題解決」のことではありません。「望ましい成果を創造すること」です。

これ、どういう意味?
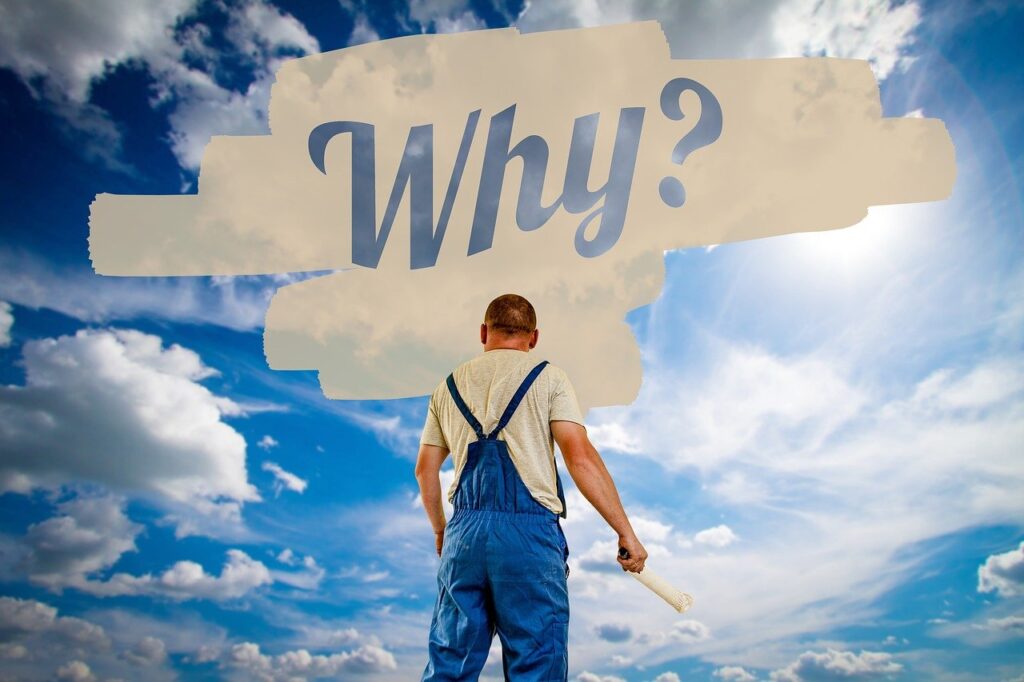
のりせんは、いままで会議を開く目的は、「問題を解決すること」だと思ってました!
問題を解決すれば、「物事はうまくいく、話はまとまる」と。
でも、「話をまとめるということと、問題を解決するということは、イコールではない」のです。
「話がまとまる」ための心構えは、「問題解決」のための心構えとは根本的に異なる。
「問題解決」が厄介なものを取り除こうとするのに対し、「話がまとまる」考え方は望ましい成果を生み出そうとする。
これまで、のりせんは問題を解決しよう、終わらせようとするあまり、論理的な筋道を立てて、話の結論を出すことに一生懸命になってました。
でも、結局は、遠回りになっているのです。
次から次へと問題が発生して、目の前の問題を解決するために、必死になると、そもそもの目的を見失ってしまうのです。
時間がいくらあっても足らなくなるのです。
話をまとめるためには、「問題解決をしてはいけない」
それでは、具体的に、話をまとめるためのコツを説明します。
話をまとめるための準備

会議の前には、2つの準備が必要です。
① 何のために会議を開くのかを考える
② 話がまとまったとき、どうなっていたらいいのかを具体的にイメージする
それぞれ、見てみます。
何のために会議を開くのかを考える
この準備をするのとしないのとでは、会議のまとまり方がまったく違ってきます。
まずは、「何のために」と考えることが、とても大切です。
これを飛ばして、「どのように」と考えることは、とても危険で、無駄なこと。
「何のために」を、自分の頭で深く考えましょう。
自分が本当に望んでいることを知り、目的を明確にすること
話がまとまったとき、どうなっていたらいいのかを具体的にイメージする

「何のために会議を開くのか」の目的が自分の中ではっきりとわかったら、次に、目的を達成した後の姿を強く具体的にイメージすることが大切です。
イメージを作り上げる方法を並べます。
① イメージを言葉と数字で具体的に表す
② 未来をでっち上げる
③ 思いっきりわがままに考える
それぞれ見てみましょう。
イメージを言葉と数字で具体的に表す
頭の中でぼやっと考えているイメージを、具体的な言葉と数字で書き出してみることが大切です。
ノートやパソコンに、片っ端から書き出してみることです。
イメージを、言葉や数字に置き変えると、より将来の姿がはっきりと見えてきます。
未来をでっち上げる
将来どうなりたいのかを予測するのではなく、未来をでっち上げることが大切です。
予測すると、狭い視野でしか、物事が見えなくなります。
既定路線の延長で考えると、イメージする将来も小さいものになってしまいます。
ぜひ、大きな未来を思い描いてみてください。
思いっきりわがままに考える
常識にとらわれず、頭のねじを何本かはずして考えることが大切です。
日本に長く住んでいる人は、日本の社会常識にとらわれているので、発想が極端にせまくなります。
常識というしがらみにとらわれていると、自由に考えることができなくなります。
子供のときにように、奔放な発想でわがままに考えていきましょう。
話をまとめるための行動
ここからは、会議の席で、話をまとめるためにどのような行動をすべきか、特に参考にした内容を紹介します。
① 組織に動いてもらう
② 相手の立場に立つ
③ 話を聞く
④ 言葉をマスターする
それでは、一つひとつ説明します。
組織に動いてもらう

会議は、組織を相手に議論することになりますが、その際、成功の鉄則があります。
・組織そのものを相手にしない
・集団を構成する一人ひとりの個人を相手にする
これは、会議をまとめる上で、とても大切な心得です。
組織は、ときとして無能な行動に走ります。
「忖度(そんたく)」という言葉に象徴されるように、組織としての総意は、成功しないことが多いのです。
なので、相手にするのは、組織でなく、個人です。
組織の中で無関心な傍観者の一人を、役割を持った協力者に変えることです。
個人を、表舞台に引っ張りだしましょう。
相手の立場に立つ

次に、話をまとめる上で大切なことは、相手の立場に立って考えるということです。
それは、つまり「思うこと」。
大切なのは、「思う」ことです。相手の話を聴いて、理解して、気持ちを感じ取ります。
とても心に刺さりました。
司会をしているとき、自分の考えや思いが強くなって、人の意見を聞こうとせず、自分の考えを押し通そうとすることがよくあります。
でも、そんな会議で無理やり押し付けた結論がうまくいくはずはないのです。
① 相手の不安を理解する
② 相手が何を欲しているかを理解する
上の2つを理解することで、相手と信頼関係が築けます。
信頼関係があればこそ、話もまとまっていくのです。
話を聞く
信頼関係を築くためには、相手の話を深く聞くことが大切です。
自分の「言う」が先行すると、自己主義に陥り、信頼関係が築けません。
意識的に、「言う」を制御することです。
そして、相手の話を心から聞くことです。
言葉をマスターする
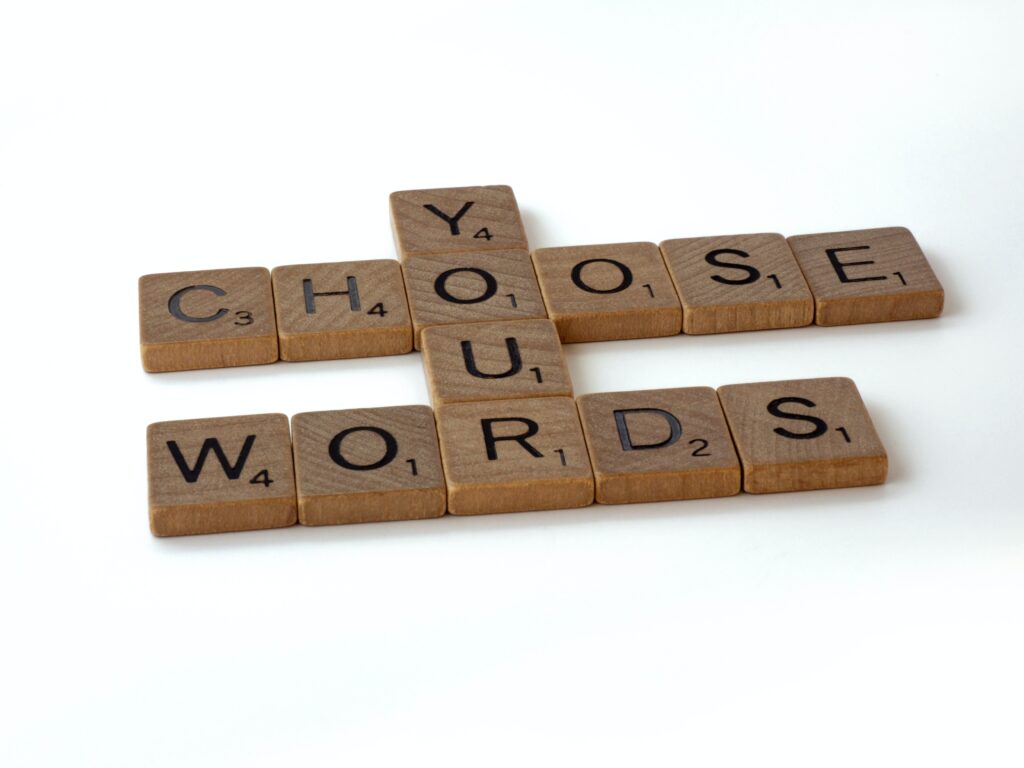
話をまとめるためには、言葉の使い方をマスターすることが大切です。
自分のメッセージや思いを相手に伝えるため、言葉の使い方を工夫しましょう。
日本語が話せるだけで満足するのではなく、あらゆる場面で、それに合う言葉を選んで、発言する。
説得するための理屈っぽいスピーチとは違う、納得感を促す言葉を選ぶことです。
まとめ
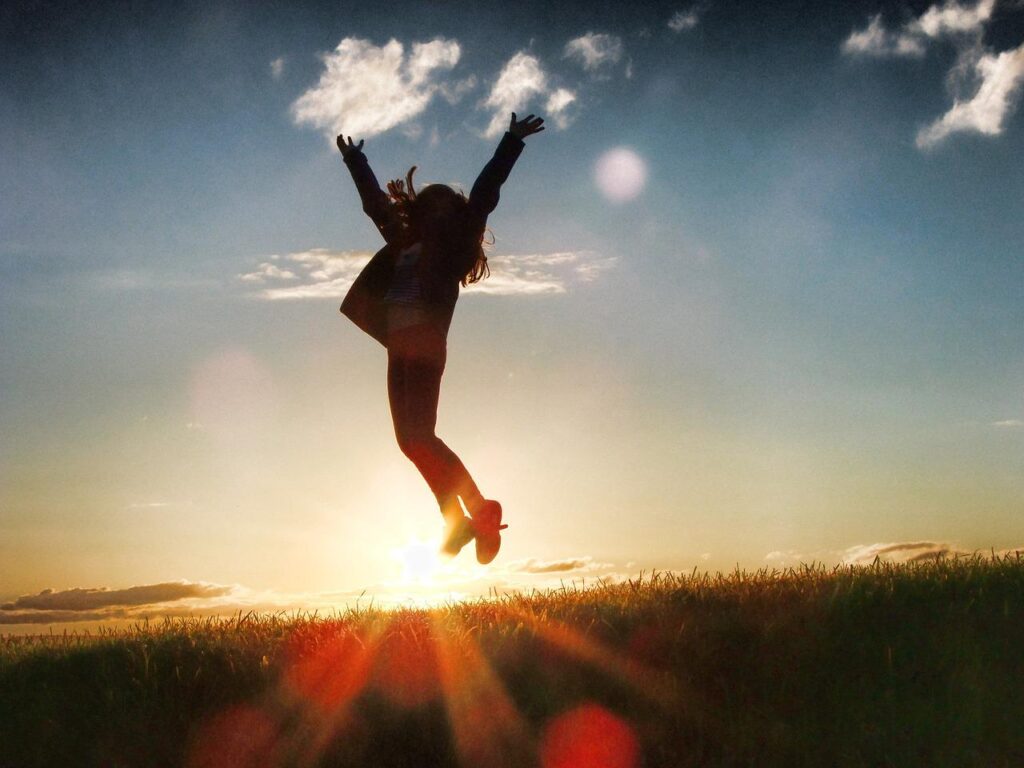
ファシリテーターとして、会議で話をうまくまとめるためのコツをまとめました。
1.話をまとめるための準備
① 何のために会議を開くのかを考える
② 話がまとまったとき、どうなっていたらいいのかを具体的にイメージする
2.話をまとめるための行動
① 組織に動いてもらう
② 相手の立場に立つ
③ 話を聞く
④ 言葉をマスターする
この本は、ファシリテーターとして、会議に望む前の準備、実践の中でどう考えればいいかがわかりやすく書かれています。
ファシリテーターとしての技術的な書籍は多く存在しますが、この本は、「人は気持ちで動く」をもとに、人を動かすためのコツに重きを置いた内容となっています。
のりせんが参加する話がよくまとまる会議は、目的が参加者みんなに共有化されていて、お互い信頼しあっていることが多いです。
会議で悩みを抱えている方は、ぜひ、読んでみてくださいね。
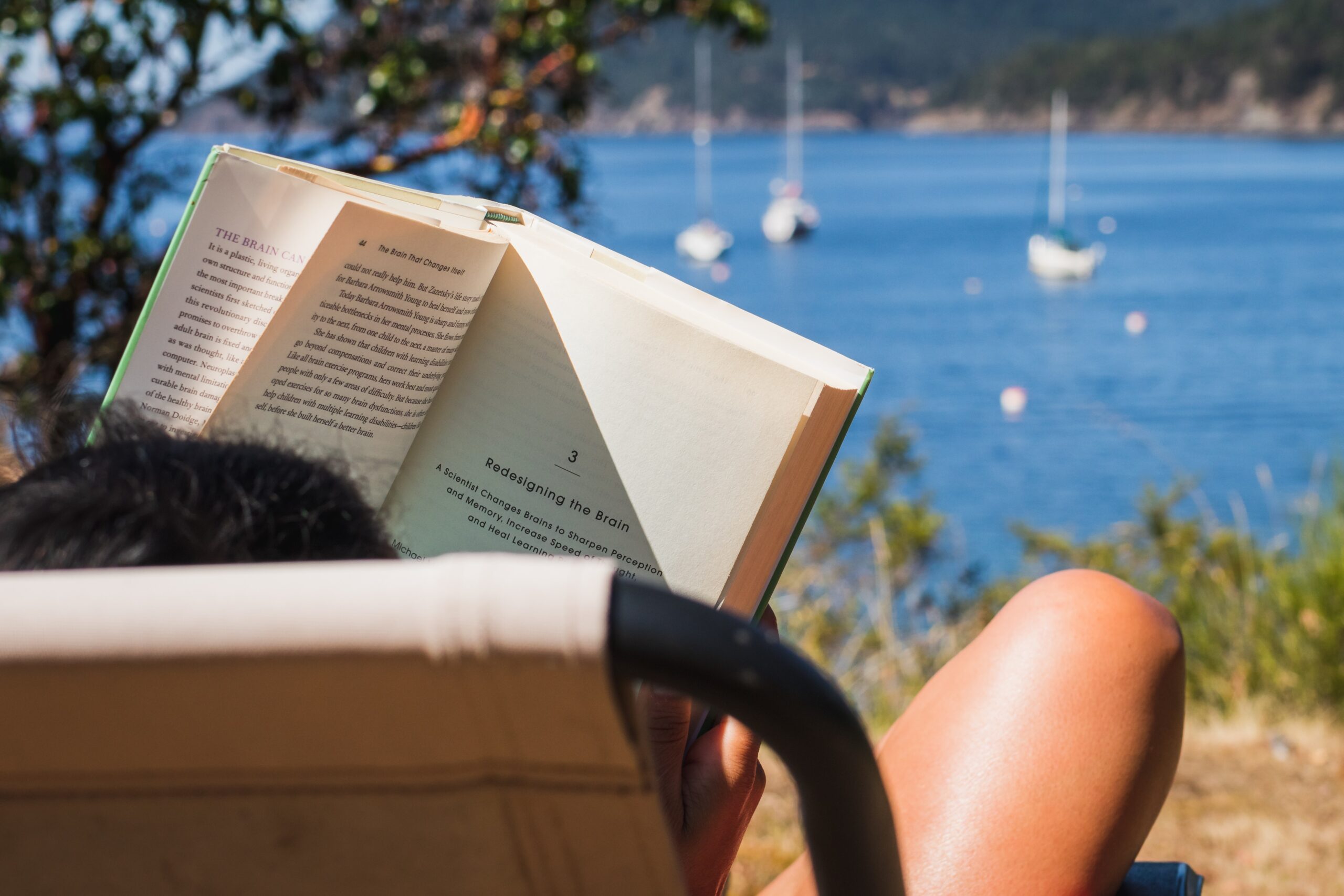

コメント